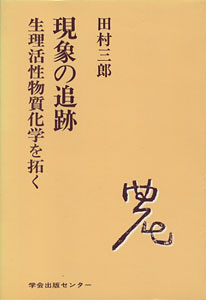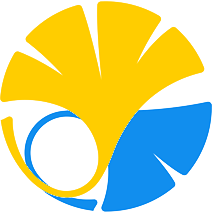FAQ
研究生活について Q 研究はどのように始まるのですか?A 研究室ではいくつか興味をもっている研究題材があります。多くの学生は配属されたあと、その中からテーマをひとつ選んで研究を始めます。学生は最初の数ヶ月〜半年は教員、研究員、学術専門職員や先輩から指導と助言を受けながら研究を進めますが、慣れてきて自分で新しい仮説を設定し、自らテーマや目標を立ち上げる学生もいます。もちろん(研究予算が許す限りですが)意欲的な学生が当研究室の既存のテーマにはない題材をもちこんで研究することも歓迎しています。Q 何を目標に研究すればいいでしょうか?A 一言で言えば「人によって違う」ですが、パターンはあります。例えば、「研究そのものが目標」になりうると思います。サッカー選手は育成年代、現役生活を経て、次世代の教育や一般へのサッカーの普及活動などに向かうケースがあると思います。同様に、研究は何千年も昔から続く本質的な人間活動ですので、それ自体が目的であり、今後も社会を駆動する振動子であり続けるはずです。また、目標が「お金を稼ぐ」であっても良いかもしれません。研究は、好奇心に従って始めた初期は、「どのように役に立つのか」まったく想像できない場合があります。しかし、GFPやCRISPRのようにお金に換算する事すら難しい程の莫大な価値を生み出す研究もあります。もしくは、「良い就職先を探すため」かもしれません。第一線の研究は世界的にもユニークなものであるため、教育材料としても独特で最良のものになります。社会に出る前に、誰も正解がわからないことについて答えを出そうとする、という経験は唯一無二の貴重なものになります。Q 学会に参加できますか?A 研究室では主に分子生物学会(例年12月開催)、植物生理学会(例年3月開催)、農芸化学会(例年3月開催)等に参加しています。学生は研究室に所属したのち、研究成果を出してまずはこれらの学会で発表することが目標になります。また、研究が進展すれば世界各地で開催される様々な国際学会にも参加する機会があり、研究室のslackを通じて参加を募ります。Q 論文はどのようなタイミングで書きますか?A 通常、論文はある程度研究成果がまとまったタイミングで書きます。当研究室の場合、着目した特定の生命現象に対して、原因物質を特定できたときに論文を書くことが多いです。インパクトの高い科学雑誌への論文掲載を目指す場合、ときには受理されるまで一年近くかかる場合もあります。精魂を込めて書いた論文が受理されたときは喜びひとしおです。Q 研究室にコアタイムはありますか?A 特に設定しておらず,個人の自由です。学生や研究者は自身の判断で研究や休みのスケジュールを組みます。研究室の共同作業等(掃除、一斉廃棄など)は、平日10〜17時の間で行われます。Q ゼミ等はありますか?A 研究室では週に一回、研究報告とジャーナルクラブ(論文を読んで紹介する勉強会)をやります(教室会議と呼んでいます)。教室会議では教員、研究員、学生がローテーションで発表しますが、大体二ヶ月に一回ぐらい順番が回ってくる程度の頻度です。このような発表の機会が、対外的な成果公表や学位審査、あるいは社会に出るときのトレーニングとして大切な意味をもちます。大体、毎回2−3時間程度研究について議論しています。Q 夏休みはありますか?A 研究室では8月の間と3月は教室会議は開催していません(ただし、3月の卒研発表時は開催します)。それらの期間はもしかすると夏休み?あるいは春休み?にあたるのかもしれませんが、特に通常時と変わらず、メンバーは自身の判断で研究を長期的にマネジメントして必要に応じて休みを取ったりしています。体調管理も研究にとって重要です。キャリアについて Q 卒業生はどのような進路に進みますか?A 研究者、製薬や食品等のメーカー、IT企業、公務員など非常に多様です。Q 修士課程から研究室に入りたいのですが大丈夫でしょうか?A これまでもそういった修士課程進学者を数多く受け入れていますので、まったく問題ありません。何か不明点があればこちらのフォーム からお問い合わせください。Q 博士課程から研究室に入りたいのですが大丈夫でしょうか?A こちらも、これまで学内外から数多くの博士課程進学者を受け入れていますので、まったく問題ありません。何か不明点があればこちらのフォーム からお問い合わせください。Q 博士課程に進みたいのですが、金銭的な不安があります。A 博士課程進学者には日本学術振興会特別研究員やSPRING GXといった経済的なサポートがあります。当研究室の在籍学生はそれらの支援を受けています。申請をサポートしますので、気軽に相談してください。Q 博士課程に進みたいのですが、ロールモデルが少なく不安に思っています。A たしかに、2000年代前半の就職氷河期以降、国内からの博士課程進学者は減っていて、不安に思うかもしれません。では、どうやって指針を探したらいいのでしょうか?研究室の歴史について Q 研究室はいつ始まったのですか?A 「生物有機化学研究室」は1924年,薮田貞次郎 先生(1888−2977)が当時の農産製造学講座の教授に就任された時に実質的に始まりました。なお、系譜上はさらに遡って古在由直 教授(1863-1934)が1900年に農産製造学講座を開講されたことが最初、とも言えます。古在教授は足尾高山鉱毒の調査や、1920年から8年間東京帝国大学総長を勤め上げられたことでよく知られています。1924年に農産製造学講座が開設された後、住木諭介 教授が在籍されていた1954年には「農産物利用学講座」に改称、田村三郎 教授が在籍されていた1971年に「生物有機化学講座」に改称されました。Q どのような研究が行われてきたのでしょうか?A 薮田教授と住木教授はジベレリンの結晶化に世界に先駆けて成功しました。また、田村教授はタケノコから植物の内生ホルモンとしてのジベレリンを単離精製し構造を明らかにしました。これらの研究は,植物ホルモンという研究分野を切り拓きました。また、田村教授の時代に植物、昆虫や海産無脊椎動物など多様な生物における幅広い生命現象が研究対象となり、その後の研究の礎になりました。1977年に四代目教授に就任された鈴木昭憲 先生は昆虫の脳ホルモンや植物の自家不和合性の研究において、重要分子の同定を行いました。鈴木教授の脳ホルモンの研究は「ペプチド科学」といった現在の重要な分野の先駆けとなりました。1997年に五代目教授に着任した長澤寛道先生は昆虫の脳ホルモンの同定を行った後、甲殻類、貝類や魚類などの様々な生物が鉱物をつくる現象に着目し、「バイオミネラリゼーション」という研究分野を立ち上げました。2017年に着任した六代目の高山誠司教授は、植物の自家不和合性をモデルに「ゲノム相関」といった概念の新しい時代のバイオサイエンスの先駆けとなる研究を行ってきました。また,世界で初めて植物の種間の生殖障壁機構の存在を証明し、「植物生殖科学」の新しい潮流を生み出しました。このように、研究室では「生命現象の追跡」を哲学として、新しい研究分野を切り拓くことをモットーとして研究が行われてきました。「現象の追跡」田村三郎先生著
1970年代以前の研究室の足取りがわかります